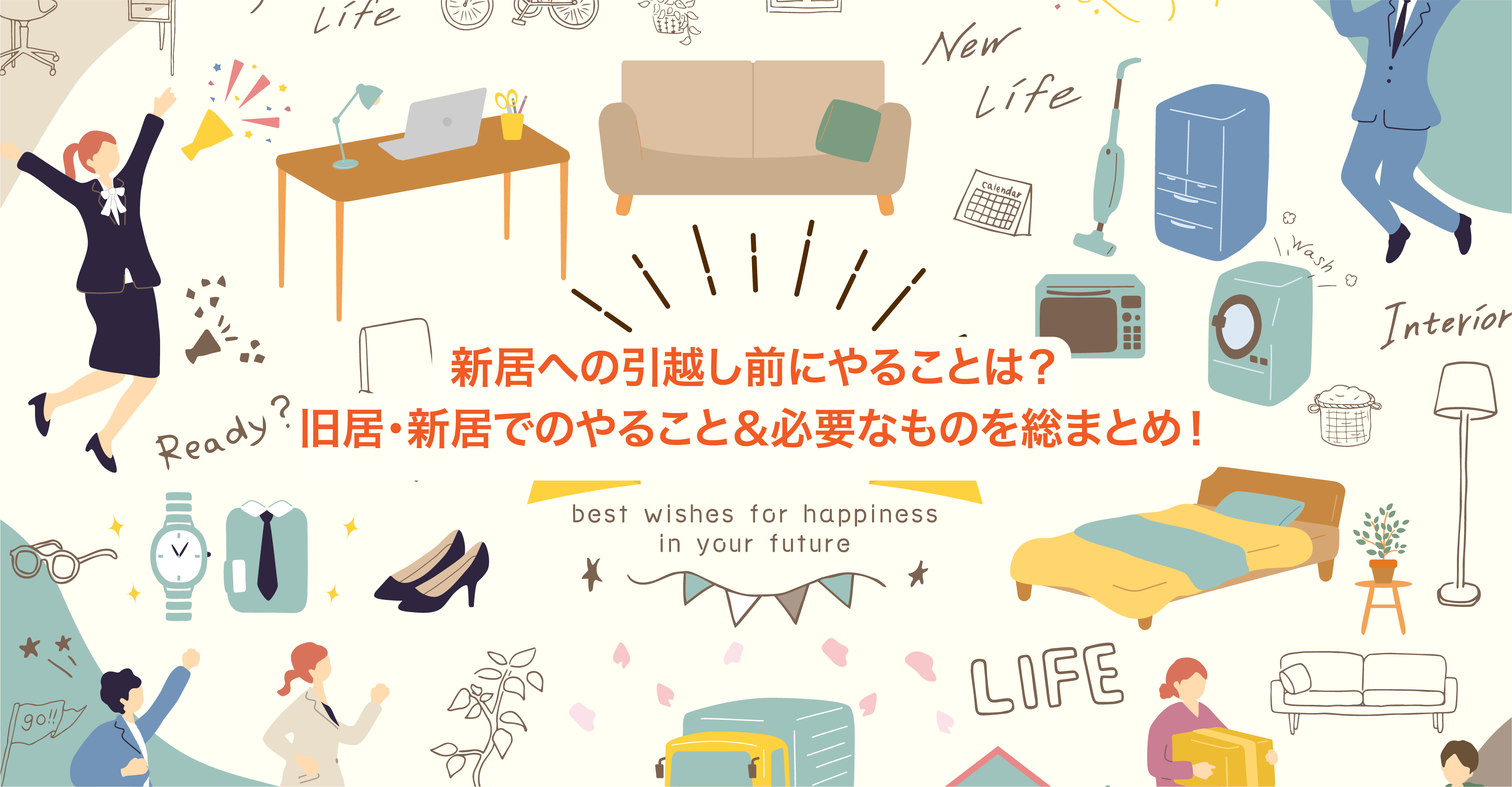
新生活に向けて引越しが決まったら、引越し業者選びに荷造りだけでなく、今住んでいるところの電気・水道・ガスなどライフラインの解約手続きの他、役所への住所変更手続きなどさまざまな手続きが必要です。新居に引越しした後も必要な手続きを忘れてしまわないよう引越しの前からあとまでの流れを「やることリスト」にまとめました。各種手続きや段取りを確認して効率よく引越し準備を進めましょう!
引越し1か月前に行うこと
1引越し業者の手配と予約
(手続きに必要なもの:見積依頼、引越し準備
届け依頼先:引越し業者)
まずは引越し業者の見積もりから始めましょう。複数の引っ越し業者を比較したり見積を取ったりしておくことが大切です。春の引越しシーズンは引越し業者のスケジュールがいっぱいで予約がとりづらいので、希望の日程が抑えやすいように早めに依頼をしましょう。
2登記申請必要書類準備
(手続きに必要なもの:社宅の場合 会社に申請)
届け依頼先:引越し業者)
賃貸住宅の場合⇒賃貸契約書 社宅の場合⇒社宅証明書

3現住所の解約・退去手続き
(手続きに必要なもの:契約時の契約書
届け依頼先:現状の管理会社)
引越し日が決まったら、今住んでいるお部屋の解約手続きを行いましょう。一般的に1か月前の解約予告が必要です。物件の管理会社ごとに解約申込方法は異なりますので、事前に確認しておきましょう。

4駐車場の解約手続き
(届け依頼先:現状の管理会社)
引越し日が決まったら、今借りている駐車場の解約手続きを行いましょう。一般的に1か月前の解約予告が必要です。物件の管理会社ごとに解約申込方法は異なりますので、事前に確認しておきましょう。
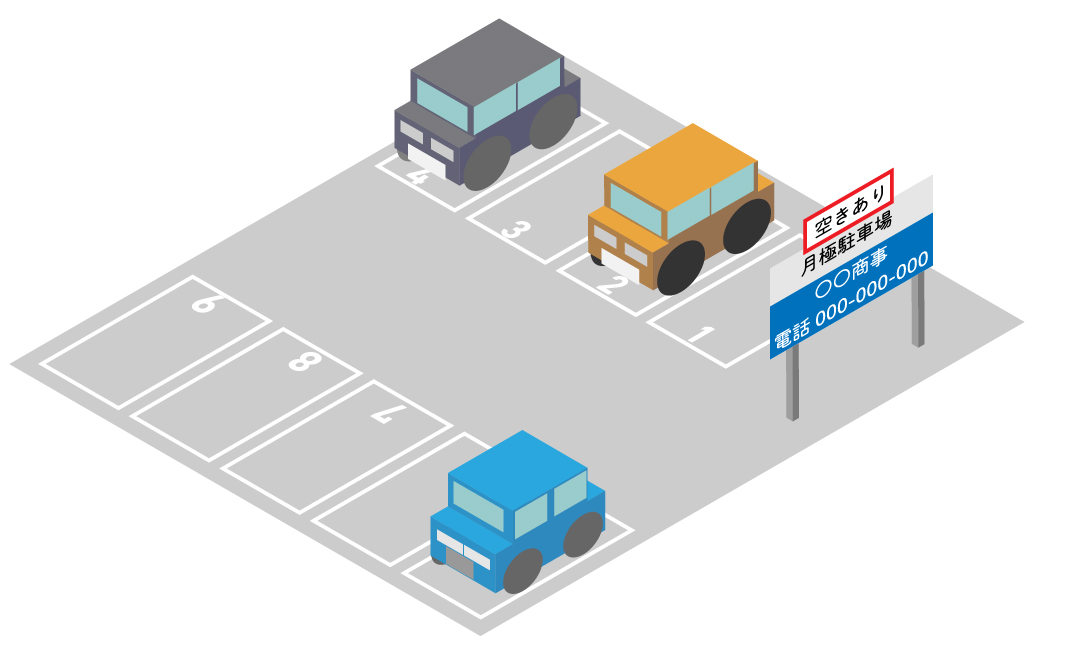
5不用品・粗大ゴミの処分
(届け依頼先:自治体、専門業者へ)
今まで使っていた家具などを粗大ごみとして出す場合はお住まいの自治体に連絡する必要があります。自治体によっては収集日が限られることもあるため、早めに確認しましょう。まだまだ使えるものはリサイクルセンターやフリマアプリの活用も有効です。

6固定電話、インターネット移転
(手続きに必要なもの:契約者情報
届け依頼先:NTT、契約プロバイダ先)
固定電話は、同一市町村外に転居する場合は電話番号が変わる可能性があるため、前もって新しい番号も確認しておくと良いでしょう。インターネット開栓は会社によって解約手続きが違うので、早めに確認して手続きをしましょう。また、モデムやルーターをレンタルしている場合は、返却しなければなりませんので機器の確認もしておきましょう。
7美術品・精密機器の移動
(届け依頼先:専門配送業者)
一般の家財とは別に専門の梱包運搬業者への依頼が安心です。

引越し1〜2週間前に行うこと
8電気、ガス、水道などライフラインの移転
(手続きに必要なもの:ガスの開栓は立会いが必要なので、
事前に連絡必要
届け依頼先:電気、ガス、水道会社)
電気・水道・ガスなどのライフラインの転居手続きを行う時期は、約2週間前が目安です。解約手続きを忘れると転居後も出費が発生しますので注意しましょう。手続きは電話やインターネットなどで行えます。その際、現在契約しているライフラインのお客さま番号を手元に用意しておくとスムーズです。

9エアコン設置の準備
(エアコン業者:
商品購入 取付場所の確認 工事業者に予約)
エアコンの取り外し・取り付け作業は、引越し業者、あるいはエアコンの専門業者や家電量販店へ依頼するのが一般的です。引越し業者に依頼する場合は、その費用が引越しの見積りに含まれているか確認しておくことが大切です。
また、10年近く使用している場合は、使用状況や耐用年数、引越し先のお部屋の広さによっては引越しのタイミングで買い替えを検討してもよいかもしれません。
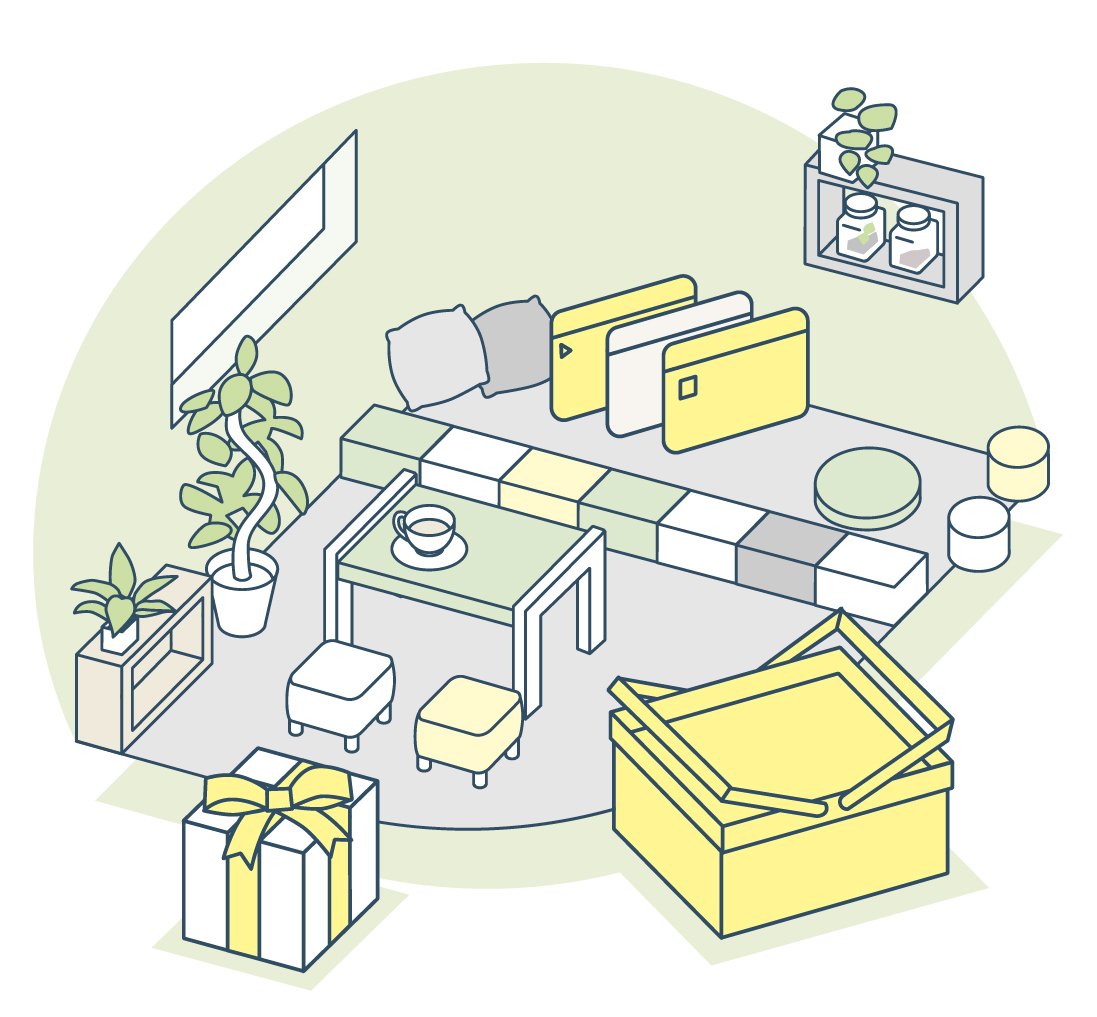
10新生活用品(家具・家電)の準備
新居への引越しに合わせて家具・家電も新居を一新したいと考える人も多いでしょう。引越し作業をスムーズに行うために事前に家具・家電の購入や配置決めをしておくとよいでしょう。
11転出、転居届
(旧住所の市区町村役所:印鑑、本人確認書類)
同じ市区町村内での引っ越しは「転居届」、異なる市区町村への引っ越しは「転出届」を役所に提出します。最寄りの役所の窓口にて用紙をもらいましょう。引越しの1~2週間くらい前には済ませておくと安心です。
「転出届」を出すことでもらえる「転出証明書」は、転居先で転入届を出す際に必要なので、なくさないようにしましょう。

12国民健康保険の手続き
(旧住所の市区町村役所:本人確認書類)
国民健康保険に加入している世帯は、「異なる市区町村へ引越しをする場合」は、引越し前の役所で「資格喪失手続き」を行い、その後引越し先の役所で「加入手続き」をそれぞれ行います。
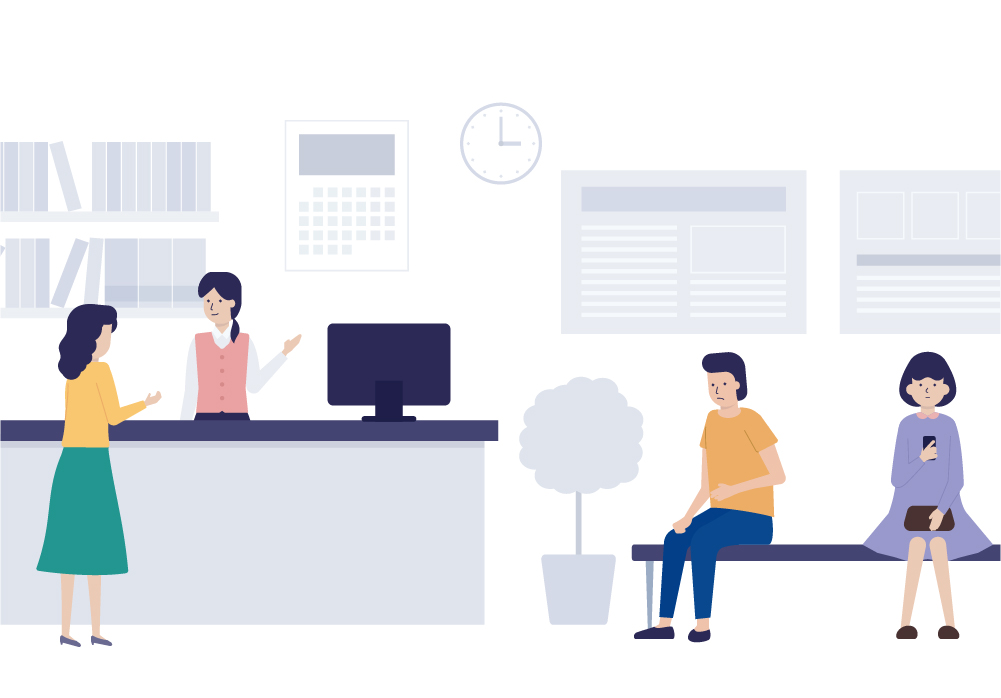
13子どもの転園・転校届
(旧住所の学校:在学証明書一式等)
公立の場合は、学校から「在学証明書」「教科用図書給与証明書」をもらいましょう。私立の場合は、各学校によって手続きの方法が異なりますので、事前に確認しておきましょう。
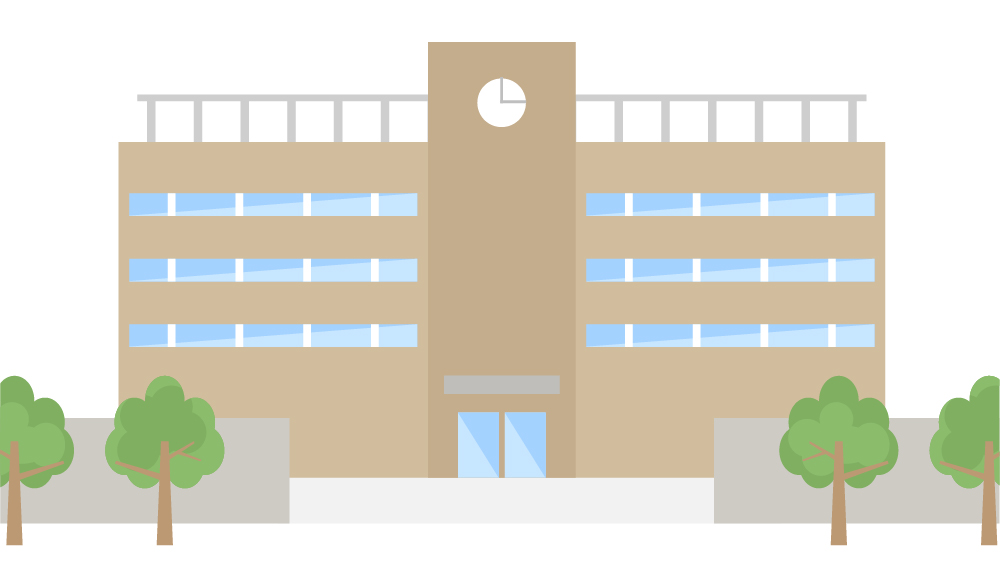
14郵便局へ転居届
(旧住所を所轄する郵便局:郵便物所定の転出届け)
新住所が決まったら、転送届を出して郵便物の転送依頼をしましょう。指定した日から1年間は、旧住所に届いた郵便物を新居に転送してくれる無料サービスがあります。
15新聞の解約、清算
(新聞販売店)
新聞の手続きは、現在配達をしてもらっている販売店にかならず解約手続き、もしくは配達先の変更手続きを行いましょう。新聞契約は原則として月単位となっていますので、引越しをする前月までに手続きを済ませるのがいいでしょう。

16荷造り
季節外の衣類や家電など使っていないものや使用頻度の低いものから優先的に荷造りを始めましましょう。うっかり必要なものを詰め込んで慌てて取り出すことのないように、何から荷造りするか順番を決めておくとよいでしょう。

不動産に関するご相談はリビングライフへ
引越し当日に行うこと
17旧住所の明け渡し
(契約時の管理会社:鍵の返却)
旧住所が賃貸の場合には、荷物をすべて出し終わった後に不動産会社と立ち合い清算を行います。あらかじめ時間の打ち合わせをしておきましょう。
18旧住所での電気、ガス、水道料金の精算
(契約時の管理会社:鍵の返却)
ガスの閉栓手続きは、すべての搬出作業が完了したら部屋にあるガスの元栓を閉めます。ガス会社の立ち合いが必要な場合がございます。精算方法は会社によって異なりますが、現金精算のみの場合もあるため、解約の連絡をするときに支払い方法を確認しておくのが安心です。
水道の閉栓手続きは、基本的に立ち会いの必要はありません。ただし例外として、外部から水道メーターが確認できない場合は立ち会いが必要となりますので、立ち会いが必要かどうか管轄の水道局に事前に確認しておくと良いでしょう。
旧居の電気は使用停止日当日まで使用できます。部屋を引き払う際はアンペアブレーカーを落として退去しましょう。電気料金は、前回の検針日から最終使用日までの電気使用分を日割りで計算したものが請求されます。

19新住所での電気、ガス、水道の確認
(契約時の管理会社:鍵の返却)
新住所のライフラインの住所変更手続きを忘れてしまうと、引越し当日に、電気・ガス・水道が使えないこともあるので注意が必要です。ライフライン開通において電気・水道は立ち会い不要で使用できるケースが多いですが、ガスの開栓には立ち合いが必要です。事前に予約していた時間に立ち会いをしましょう。
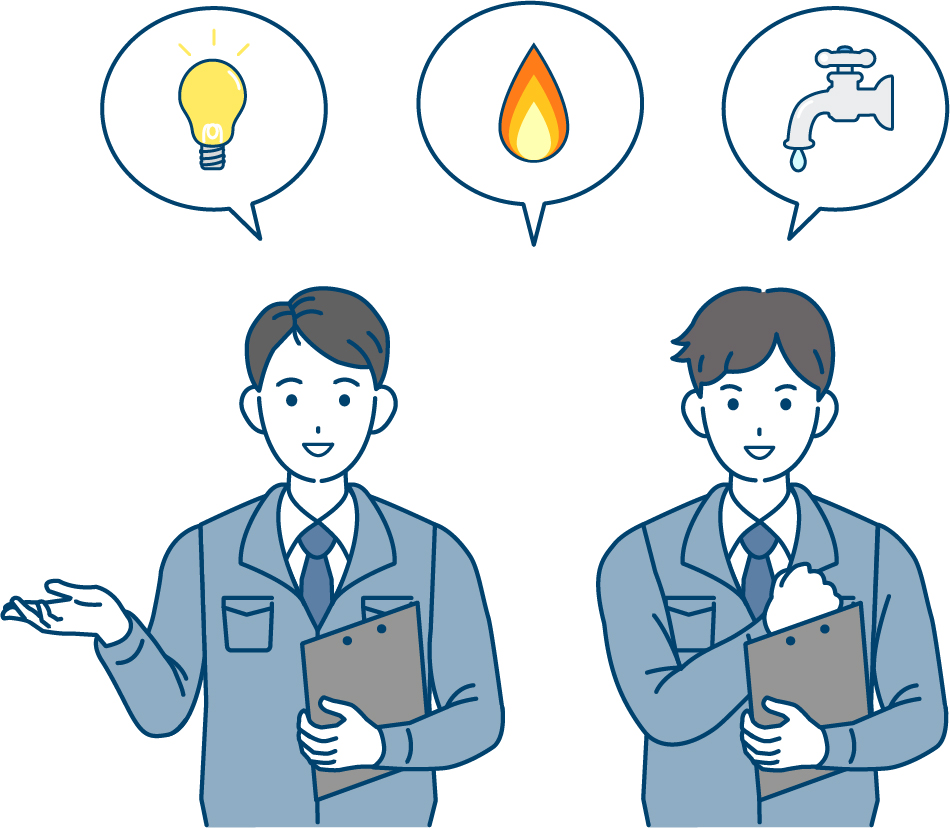
引越し後に行うこと
20転入届
(新住所の市区町村役所:転出証明書、印鑑)
異なる市町村への引越しの場合は、引越し後14日以内に引越し先の役所に「転入届」を提出します。前住所の役所で受け取った「転出証明書」と身分証明書、印鑑を準備しておきましょう。
21マイナンバーの住所変更
(新住所の市区町村役所)
転入届の手続きと一緒に行うといいでしょう。

22国民健康保険加入手続き
(新住所の市区町村役所:転出証明書、印鑑)
転入届の手続きと一緒に行うといいでしょう。
23印鑑登録
(新住所の市区町村役所:必要な証書、印鑑)
転入届の手続きと一緒に行うといいでしょう。
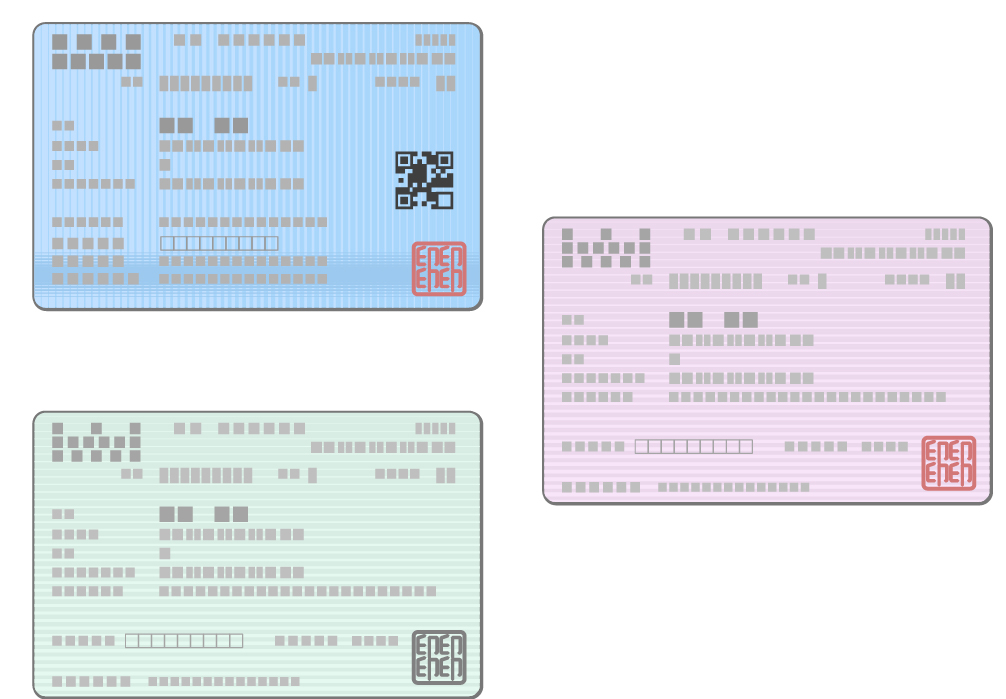
24福祉関係手続き(児童手当、年金等)
(新住所の市区町村役所)
転入届の手続きと一緒に行うといいでしょう。
25子どもの転入学届
(転入学先:在学証明証、新住所の住民票等)
公立の小中学校の場合は、在学中の学校からもらえる「在学証明書」「教科用図書給与証明書」と、役所で住民票の手続き時にもらえる「転入学通知書」と一緒に転校する学校へ提出します。
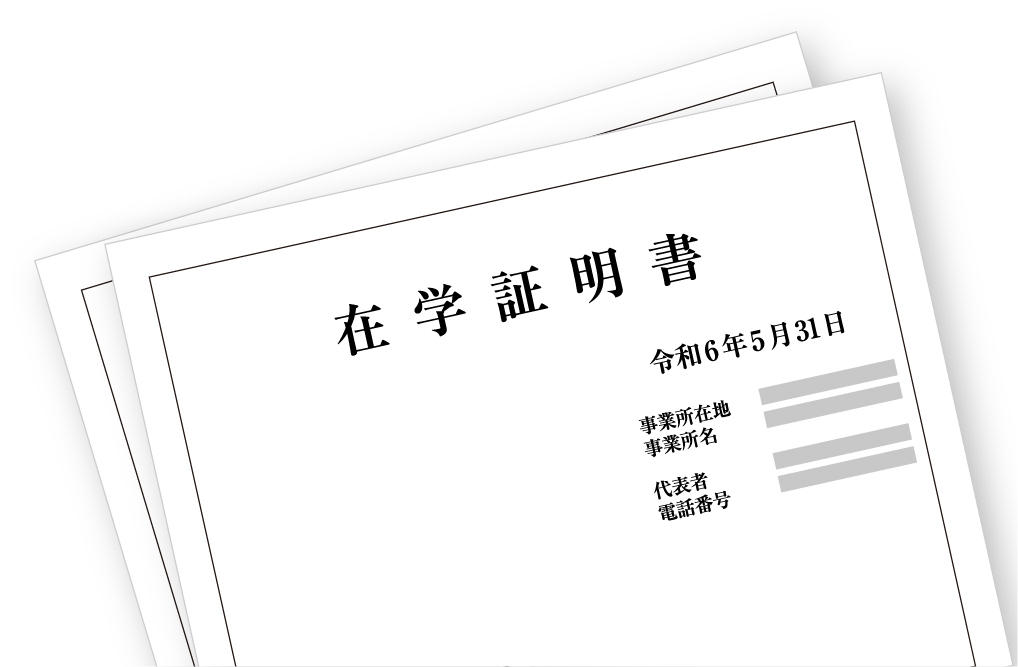
26運転免許証の住所変更
(新住所管轄警察署、運転免許センター:
新住民票、写真、免許証)
運転免許証の住所変更の際に新住所の「住民票」などが必要になります。役所での手続きの際に取得しておきましょう。

27自動車の登録変更
(新住所所轄陸運支局:
新住民票、変更登録申請書、住民票等)
①自動車保管場所証明(車庫証明)申請手続き、②自動車の登録変更手続きが必要になります。車庫証明の発行は契約駐車場を管理する不動産会社から発行してもらうことが多いので確認しておきましょう。
28銀行口座やクレジットカードの住所変更
(取引銀行、クレジットカード会社:
印鑑、通帳、住所変更後の運転免許証)
銀行口座やクレジットカード、各種保険、携帯電話など住所変更の手続きをしておきましょう。インターネット上で簡単に手続きできるものも増えていますので活用しましょう。有効期限切れなどで新たなカードが発行された際に、住所不定で届かなかった場合、再度発送してもらえないケースもあります。

29ご近所へのあいさつ
引っ越しのタイミングでご挨拶に伺うことで、ご近所の方の顔がわかりコミュニケーションがとりやすくなります。できれば当日に行っておきたいですが、引越しの時間帯によっては翌日以降に行くようにしましょう。

不動産に関するご相談はリビングライフへ

